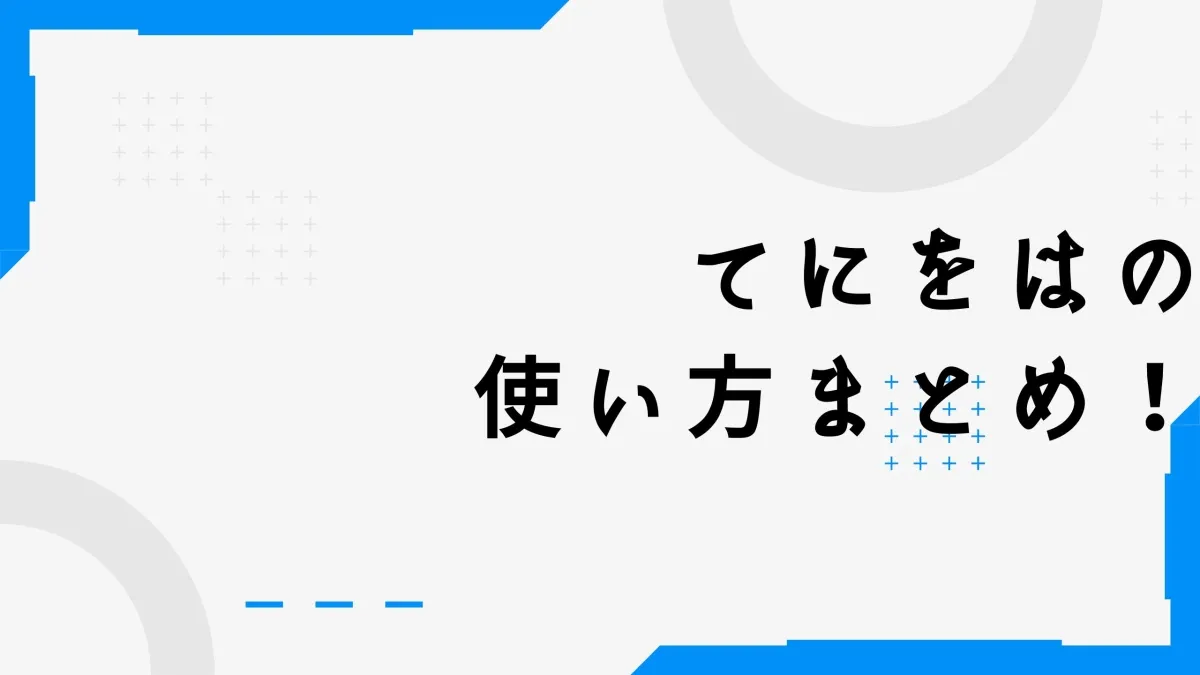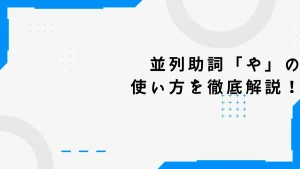- そもそも「てにをは」って何?
- てにをはを使い分けるコツが知りたい!
- 正しいてにをはを身につける方法をも教えてほしい
当記事では、「てにをは」の意味や使い分け方を、現役のWebライター・編集者が徹底解説。さらに正しい「てにをは」を身につけるためのトレーニング方法も紹介します。
「てにをは」の使い方をマスターし、自分の伝えたいニュアンスを読者に正しく伝わる文章を書きましょう。
まずは意味を確認!てにをはとは助詞の総称
「てにをは」とは、助詞の総称のこと。「てにをは」は、単語と単語をつなぐために使われます。
たった数文字ですが、使い方ひとつ間違えると文章の意味が変わったり、伝えたい情報を伝えられなかったりする重要な要素なのです。
具体例として、「てにをは」を正しく使っている文章と、正しく使えていない文章を3パターンずつ比べましょう。
- アイスが好き
- 時計を見る
- 有名になりたい
- アイスに好き
- 時計が見る
- 有名へなりたい
「てにをは」以外の言葉は同じ文章にもかかわらず、たった一文字が違うだけで、意味が変わる、もしくは文章として成り立たなくなりました。
伝えたいことを読者に伝えるためにも、「てにをは」をマスターしていきましょう。
てにをはの使い方次第で文章のニュアンスが変わる
「てにをは」の使い方次第で、文章のニュアンスはガラッと変わります。
たとえば下記の文章を見てみましょう。
- パスタがいい
- パスタでいい
上記の文章は「てにをは」以外同じ言葉を使っていますが、受ける印象が変わるはず。
「が」を使った文章では、とにかくパスタを食べたいという気持ちが伝わってきます。反対に「で」を使った文章からは、それほどパスタを求めておらず、どこか妥協を感じます。
このように「てにをは」の使い方次第で、読み手の受ける印象が変わってしまうわけです。
自分の気持ちを正しく伝えるためにも、「てにをは」は丁寧に選びましょう。
てにをはの一覧表
「てにをは」の一部を表にまとめました。あくまでも一部ではありますが、選ぶときの参考にしてください。
| 助詞の種類 | 役割 | てにをは |
|---|---|---|
| 格助詞 | 体言に付く | が、を、に、の、へ、と、で、や、より、から |
| 接続助詞 | 前後の文節をつなぐ | ば、とも、ど、ども、が、に、を、て、で、ながら、ものの |
| 副助詞 | 副詞のような働きをする | は、だけ、ほど、すら、しか、のみ、ばかり、など、まで |
| 係助詞 | 強調、疑問、反語の意味を添える | は、も、でも、しか、さえ、こそ、ほか、だって、ぞ、なむ |
| 終助詞 | 文末に付く | な、に、とも、の、か、ぞ、や、よ、わ、さ、せ、ね、かしら |
| 並列助詞 | 単語と単語を並べる | の、に、と、や、し、やら、か、なり、だの、とか、も |
| 間投助詞 | 感動や強調する | さ、よ、ね、な、を、や、ろ、い、ら、し |
| 準体助詞 | 体言の代用 | の、から、ぞ、ほど、ばかり、だけ、が |
上記の通り、普段何気なく使っている「てにをは」は、8種類に分かれているとわかります。
では8種類もある「てにをは」を、どう使い分けたらいいのでしょうか。
例文あり!てにをはの使い方をまとめてみた
ここでは、とくに使い分けに迷いやすい下記の7種類の「てにをは」の使い分け方を、例文付きで解説します。
- 副助詞「は」と格助詞「が」の使い分け
- 目的格を表す「が」「で」「も」の使い分け
- 目的格を表す「で」と「を」の使い分け
- 目的格を表す「に」と「を」の使い分け
- 意思を表す「が」と「を」の使い分け
- 目的地を表す「に」「へ」「まで」の使い分け
- 場所を表す「に」と「で」の使い分け
「てにをは」の扱いをマスターする際、以下の7種類をマスターすればひとまず及第点ですから、ここからスタートしましょう。
副助詞 「は」と格助詞「が」の使い分け
主語に付く助詞「は」と「か」は、対比の有無によって使い分けましょう。
格助詞「は」は、主語以外のなにかと比較・対比する場合に用い、副助詞「が」は比較するニュアンスを載せないときに用います。
実際に、「は」と「が」を使った例文を2つ挙げて、使い分け方を確認します。
- バレーボールは面白い
- バレーボールが面白い
1つ目のの文章は「他のスポーツにも魅力があるけど、やっぱりバレーボールって面白い」のようなニュアンスが伝わりますね。
一方で後者の文章からは「(他のスポーツは関係なく)とにかくバレーボールが面白い」という排他的な意味合いの文章になります。
このように、主語となる言葉に付く「てにをは」は、比較や対比のニュアンスを含めたいか否かによって使い分けましょう。
目的格を表す「が」「で」「も」の使い分け
目的格を表す助詞「が」「で」「も」は、意思や想いの強さに応じて選びましょう。イメージとしては、で<も<がの順で意思が強くなります。
では例文で使い分けを確認しましょう。
- 私はカラオケが良い
- 私はカラオケで良い
- 私はカラオケも良いと思う
1つ目の例文からは、「とにかくカラオケに行きたいんだ!他の場所には行きたくない!」という強い意志が伝わってきますね。
反対に、「で」を使った例文からは「あんま興味ないけど、他に行くところもないしカラオケで良いや」のような投げやりなニュアンスが伝わってきますね。
「ボウリングもいいけど、カラオケもいいね」と思うときは「も」を使います。
目的格を表す助詞「が」「で」「も」は、たった一文字で意思の強さを伝えられますから、適切な「てにをは」を選びましょう。
目的格を表す「で」と「を」の使い分け
目的格を表す助詞「で」「を」は、付く言葉によって使い方は変わりますが、ここではカフェでショートケーキを注文するシチュエーションで使い分け方を考えてみましょう。
- ショートケーキでお願いします
- ショートケーキをお願いします
普段「何か召し上がりますか?」と聞かれたとき、とっさに出るのは「〜でお願いします」ではありませんか?もちろん間違いではないのですが、「でお願いします」は少々投げやりな印象を相手にあたえる可能性があります。
また「モンブランが売り切れてしまったから、仕方なくショートケーキを選んだ」のようなニュアンスも感じますね。
丁寧、かつ誠実な印象をあたえたいときは、「をお願いします」を選ぶのがベターです。
目的格を表す「に」と「を」の使い分け
目的格を表す助詞「に」「を」は、気持ちの強さによって使い分けましょう。さまざまな用法がありますが、ここでは「頼る」を用いた例文を2つ挙げてみました。
- 先生に頼る
- 先生を頼る
どちらの文章も文法的に誤りはありません。
「に」を使った文章は「困ったからとりあえず先生に頼ろう」というニュアンスが受け取れますね。反対に「を」を使った文章からは「とにかく先生に助けてほしい!先生お願い!」のような強い意思を感じませんか?
意思が強いなら「を」を、そうでないなら「に」をと使い分けてみましょう。
意思を表す「が」と「を」の使い分け
意思を表す助詞「が」「を」は、何を主役にしたいかによって選びましょう。まずは下記の2つの例文をご覧ください。
- 私はバームクーヘンが食べたい
- 私はバームクーヘンを食べたい
どちらも「バームクーヘンを食べる」という気持ちや意思が表された文章です。
その違いは、助詞の役割にあります。
「が」は、主格を表す助詞です。主格とは、その文章のメインテーマのこと。例文をわかりやすく変換すると「私が食べたいのは、バームクーヘンだ」のように、「が」を付けることでバームクーヘンに焦点が向かいます。
一方「を」は、直接対象格を表します。直接対象格は動作の対象のことで、例文で言えば、「食べたい」を修飾する役割を担います。
つまり「が」を使うことで「バームクーヘン」が文章のメインに据えられるため、強い気持ちが表現されます。「を」はあくまでも動作の対象に過ぎませんから、そこまで強烈な欲求は感じません。
「が」と「を」の使い分けは難易度が高いので、正しく使用できれば文章力がワンランクアップすることでしょう。
目的地を表す「に」「へ」「まで」の使い分け
助詞「に」「へ」「まで」は、目的地に応じて使い分けてみましょう。下記の3つの例文をご覧ください。
- 駅に行く
- 駅へ行く
- 駅まで行く
最終目的地が駅なら「に」を使いましょう。「に」は地点を表す助詞ですから、駅に行くのが目的だと伝わります。
「へ」は方向を表しますから、駅を経由して目的地へ行く場合、「へ」が適しています。「駅に行ってから他になにかする」というニュアンスが含まれます。
助詞「まで」は、経過を表すため、元にいた場所からある地点までの移動の過程を表現したいときに使いましょう。「移動が大変だった」「車で向かった」などを伝えるときにふさわしい表現です。
「に」「へ」「まで」は目的地を表す助詞ですが、たった一文字で微妙なニュアンスの違いを表現できます。
場所を表す「に」と「で」の使い分け
場所を表す助詞「に」「で」は、方向を表すか、地点を強調したいかで使い分けましょう。例文を2つ挙げてみました。
- 入り口に集合する
- 入り口で集合する
「に」は方向を表す助詞。そのため例文は、「入り口(の方向)に集合」のようなニュアンスが含まれます。「〜へ」も方向を表しますが、「へ」にくらべると方向よりも場所の意味合いが強くなります。
一方「で」は、地点をピンポイントで表す助詞です。「集合する場所は入り口ね!」のように、場所を強調したいときは「で」を選びましょう。
方向も表したいときは「に」を、場所をピンポイントで伝えたいときは「で」を使いましょう。
てにをはを正しく使うトレーニング方法
続いては「てにをは」を正しく使うコツをつかむためのトレーニング方法を3つ紹介します。
- 本を読んで正しい日本語の使い方を味わう
- 他の人が書いた文章を添削する
- 語り手の立場を明確にする
「てにをは」を正しく使うコツが身に付けば、たった1文字でその文章のニュアンスを操れます。
以下のトレーニングを重ね、「てにをは」の正しい使い方を身につけましょう。
本を読んで正しい日本語の使い方を味わう
「てにをは」の正しい使い方のコツをつかむには、本を読むのが王道です。
本は、出版社や編集者によって校正校閲が重ねられ、幾重にもチェックされたうえで出版されるもの。そのため正しい日本語で書かれている場合が多く、文法の使い方を肌で味わうにはぴったりです。
最近では、Kindle出版のおかげで、個人でも簡単に出版できるようになりました。しかしその多くは、編集者による校正が入っていないため、「てにをは」が乱れていることもあります。
もちろんためになるKindle書籍もありますが、「てにをは」の正しい使い方をトレーニングするという観点から言えば、紙の本に軍配が上がります。
また読書には、「てにをは」の正しいコツを学べるほか、次のようなメリットもあります。
- 文章力が高まる
- 語彙力が身に付く
- 知識が身に付く
- 想像力が豊かになる
読書は一石五鳥のトレーニング方法ですから、ぜひ取り組んでみてください。
他の人が書いた文章を添削する
他の人が書いた文章を添削するのも、「てにをは」を鍛えるいいトレーニング方法です。
僕らは、自分が書いた文章を甘い目線で読みがちです。それは執筆過程の苦労や、文章を書き上げた達成感によるものかもしれません。いずれにせよ、自分の文章を客観的に読むのはなかなか難しいんですね。
反対に、他人が書いた文章にはとくに思い入れはありません。他人が書いた文章はフラットな目線で読めるため、自分の書いた文章にくらべて客観的に読みやすいのです。
自分の文章を読み返したときには気づけなかった違和感に気づけますから、ぜひやってみてください。
「人の書いた文章を勝手に添削するなんて申し訳ない…」と思うかもしれませんが、添削した文章をネット上に公開するなどしないかぎり筆者に迷惑はかかりません。
もし適切な題材が見つからないのなら、当ブログ記事を活用してもOKです。
語り手の立場を明確にする
「てにをは」を正しく使うには、語り手の立場を明確にしておくことがポイントのひとつ。
「てにをは」は、人称によって使い方が異なるからです。
- (店の立場)特売キャンペーンを実施している
- (客の立場)特売キャンペーンが実施されている
上記の文章のように、文章の主体によって「てにをは」が変わることがあります。
この文章は誰が語っているのかを意識し、適切な「てにをは」を選びましょう。
てにをはの使い方を理解して、正しい日本語文法を学ぼう!
「てにをは」をたった一文字間違えただけで、読み手の受ける印象が大きく変わることもあります。
当記事で紹介した使い分け方や、下記のトレーニング方法を取り入れて、「てにをは」の使い方をマスターすることは、文章を扱う人にとって大切です。
- 本を読んで正しい日本語の使い方を味わう
- 他の人が書いた文章を添削する
- 語り手の立場を明確にする
練習を重ね、正しい「てにをは」の使い方を身につけていきましょう。